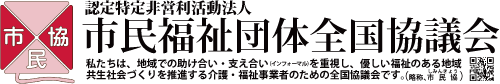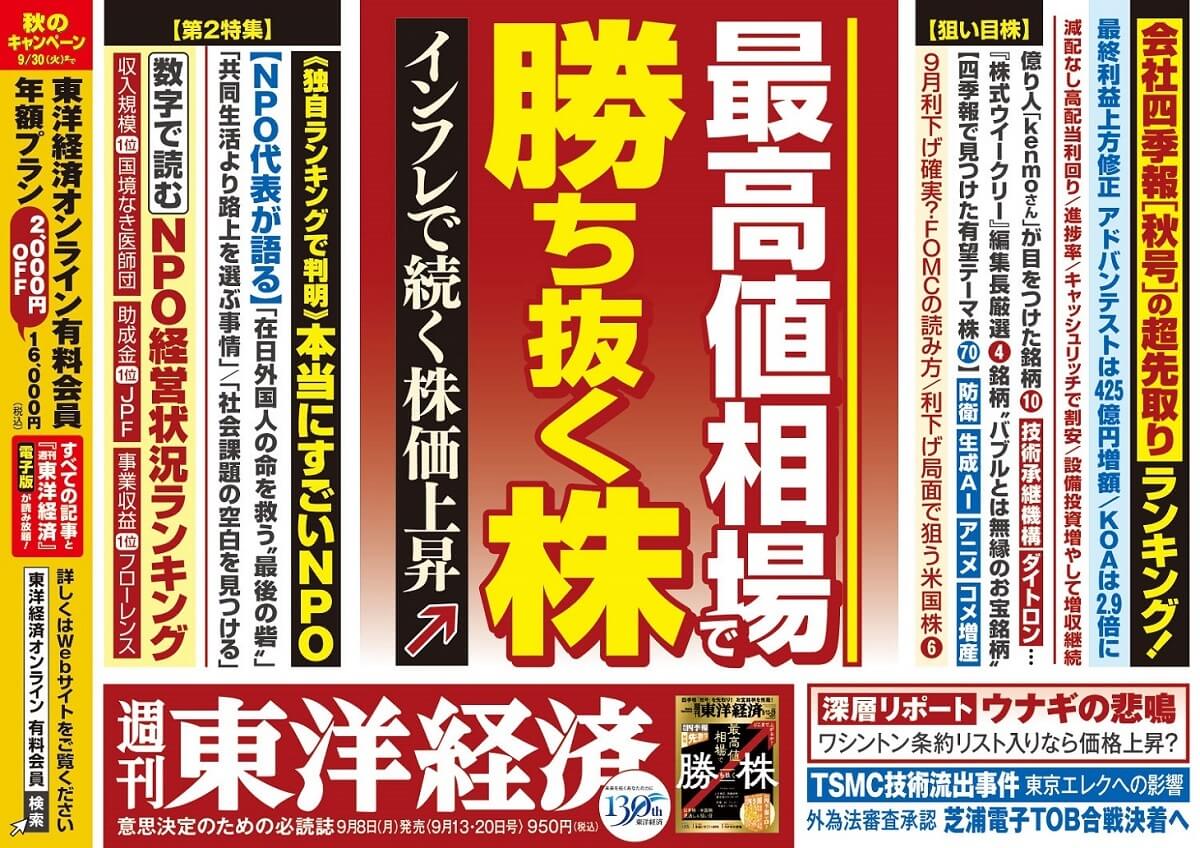第126回介護保険部会の開催に合わせ、
10/6、第322回民間介護事業推進委員会が開催され、
とよしま代表理事が同委員会委員として参加し、以下の意見を述べました。
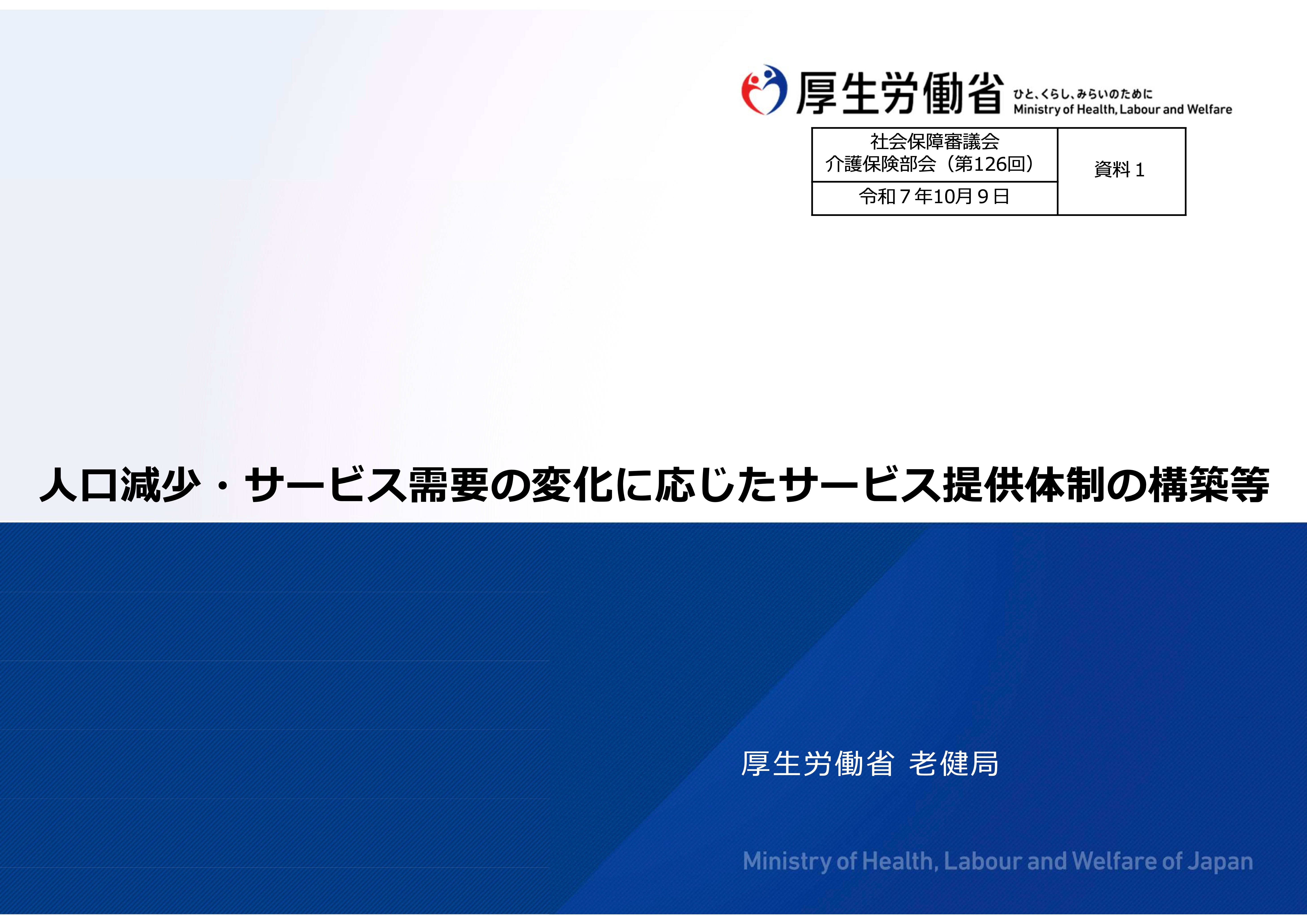
【資料1】人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等について
・論点①「地域の類型の考え方」/論点②「地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み」において、「新たな類型案」が示されているが、従来議論されていた「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3分類以外に類型を増やす必要性はあるのか。複雑にすべきではなく、これまでの3分類のみとし、例えば「A市は中山間70%、一般市30%とする」など割合で濃淡を表現するような柔軟な運用はできないのか。
・論点③「地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み」は歓迎する。人をお金で見るのではなく、地域福祉を支えていることに対しての評価は必要だ。
・論点⑤「介護事業者の連携強化」については、機能連携ではなく、論点⑥「地域の実情に応じた既存施設の有効活用」と同様に、モノの連携(コンパクトシティ構想で中心地に作る道の駅にリハビリ施設を建設し、それを各事業所が利用できる等)もできるように弾力的な運用を望む。
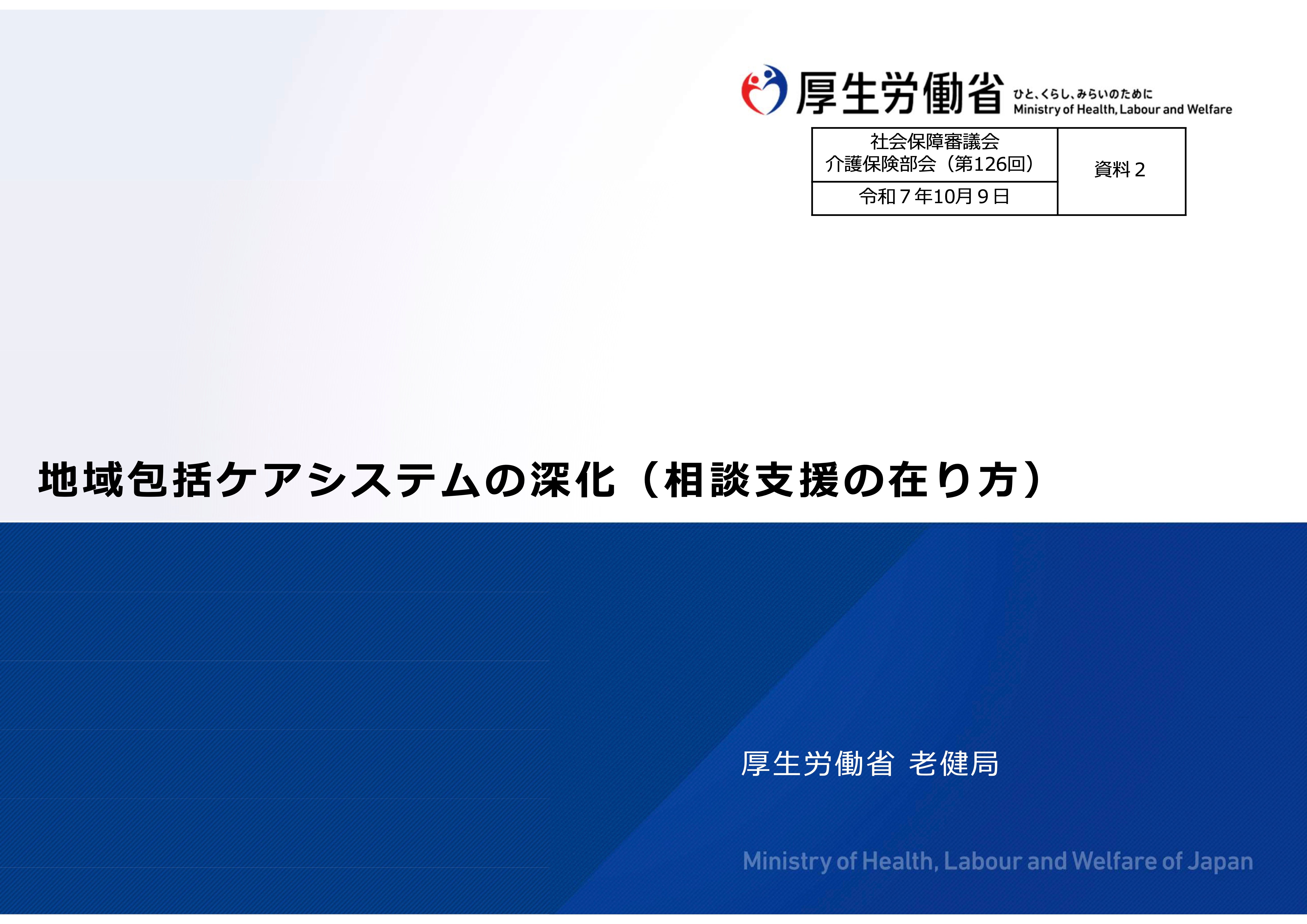
【資料2】地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)について
・論点①-i「地域ケア会議の活用推進、相談体制の充実等」において、身寄りのない高齢者等への支援に地域ケア会議の活用推進が挙げられているが、以前に、ケアマネのシャドーワーク軽減などに地域資源を使うという方針に対して「地域は打ち出の小槌ではない」と申し上げたが、今回は地域包括ケアを活用するとのことだが、他委員からもあったように既に手一杯の地域包括に押し付けるのは適当ではない。介護/医療/生活の三すくみで高齢者を支えるべきであり、居住支援事業も含めた生活分野についても体制図では対等に描くべき。
・論点②「災害等の有事に備えた地域包括支援センターの体制整備」について、地域包括にはBCPの策定義務がない現状を変え、BCP策定等の体制整備を図っていくことには賛成。介護福祉事業所においてBCPが未策定の場合には減算となるため、ほぼ全ての事業所が策定済みだが、自分たちで書いたものではないので絵に描いた餅でしかない。より実効性のあるものにするための検証や訓練などの仕組みが必要と考える。
・同じく論点②について介護保険部会でも意見があったように、福祉避難所についても課題が多い。現状は福祉避難所は二次開設となっており、これでは高齢者や障害者は発災直後は避難先が無いことになる。発災後は直ちに福祉避難所は一次開設できるようにすべき。
市民協では、これからも地域の類型の考え方、地域包括ケアシステムの深化について注視していきたいと思います。
第126回介護保険部会の資料はこちらからご覧になれます。
> 第126回介護保険部会
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html
<民間介護事業推進委員会について>
当団体らの声がけから始まった仕組みで、
厚生労働省による介護保険サービスに関する
関係団体懇談会として開かれ、
介護保険制度・報酬改定関係の意見具申などを行なっており、
当団体を含む以下の民間介護事業7団体で構成されています。
・社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会
・JA高齢者福祉ネットワーク
・一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構
・一般社団法人日本在宅介護協会
・一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会
・一般社団法人シルバーサービス振興会
・認定NPO法人市民福祉団体全国協議会
認定NPO法人市民福祉団体全国協議会(市民協)は、
一般社団法人シルバーサービス振興会にも所属しており、
上記委員会の委員として参加しています。